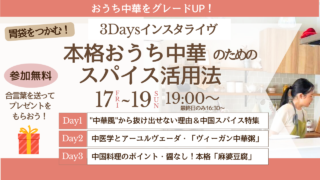海のミルクといわれるほど栄養価が高い二枚貝、牡蠣。
本稿では、牡蠣の栄養、生食と加熱用の違い、牡蠣を縮ませずに美味しく調理する方法など、知って得する基礎知識をお伝えします。
牡蠣
牡蠣は種類が多く、世界中に分布しています。
天然ものと養殖ものとがありますが、 市場に出回るのはほとんどが養殖のまがきです。
| 分類 | 貝類 |
| 栄養 | 脂質と糖質(グリコーゲン)が多い。鉄のほか、 銅、マグネシウム、ヨウ素などの無機質を豊富に含む。 |
| 主産地 | 松島湾、広島湾、志摩半島など |
| 旬 | 12~1月。うま味成分をまとめるグリコーゲンの量が増える冬が旬。「花見過ぎたらかき食うな」とあるように、5~8月は生殖巣が成熟し毒化しやすいので生食は避ける。 |
栄養
良質のたんぱく質に富み、疲労回復や動脈硬化に役立つタウリンも多く含まれています。
さらに、亜鉛、鉄、銅などのミネラル類の含有量が食品のトップレベル。
細胞の代謝を促し、免疫力を高めるなどの働きが期待できます。
生食用と加熱用の違い
調理した牡蠣もおいしいですが、生牡蠣もおいしいですよね。
けれど、市場に出回っている牡蠣なら、全て生食してもいいわけではありません。
生食用、加熱用に分かれています。
生食用、加熱用は、何が違うのでしょうか。
実は、鮮度の違いは関係ありません。
とれる海域の違いでどちらかに分かれます。
生食用
水域基準を満たした海域に限られています。
沿岸部より沖合が多いです。
沖合は餌となるプランクトンは少な目で、牡蠣の成長はゆっくりですが、安全性が高く生で食べられます。
加熱用
沿岸部で取れる牡蠣が多いです。
沿岸部はプランクトンが多いので、うまみが強く濃厚になります。
おいしい牡蠣の選び方
- 黒いヒダがしまっているもの
黒いひだは外套膜といいます。
花が開いた外套膜は、水を多く含んでいる牡蠣の証拠です。 - 色が乳白色(クリーム色)のもの
真水を含んだ牡蠣は白っぽく見えることがあります。 - 貝柱が透明のもの
安全面│なぜ牡蠣に当たるの?
牡蠣にあたるのは、ノロウイルスが存在していることがあるからです。
牡蠣にあたるかどうかは、体質と体調によります。
体質
ノロウイルスは、腸の細胞の表面にくっついて、それから感染して症状が出ます。
体質的に、腸の細胞にくっつきやすい人とくっつきにくい人がいます。
体調
免疫力が劣っている人、子供やお年寄り、持病を持っている方はかかりやすいです。
※以前ノロウイルスにかかったことがある人は抗体を持っていますが、ノロウイルスはいろいろな型があるので、必ずしもかからないとはいえません。
ノロウイルス以外にも気を付けるべきこと
蕁麻疹、お腹を壊した場合、アレルギーの可能性があります。
アレルギーの場合は、短時間で症状が出るので、すぐに病院へ。
安全に牡蠣を食べるためには
加熱しましょう。
牡蠣の中心部が85~90度で90秒以上加熱(厚生労働省の加熱基準)すると、ノロウイルスが死滅します。
おいしく食べるために知っておくべき牡蠣の特徴
縮ませない
牡蠣の体内には海からの塩分が含まれています。
真水につけると、水が塩分濃度が高い方へ移動するため、牡蠣がふくらみ、旨味が薄まります。
水をすって膨らんだ牡蠣は細胞が壊れやすくなっていて、加熱すると縮んでしまいます。
そのため、工場では洗浄からパックにつめるまで、海水につけています。
この知識は、家庭で牡蠣を扱う上でも役立ちます。
加熱しても縮まない方法・調理のポイント
- 下処理で牡蠣を塩水で洗う。
水に塩を入れて、海水の濃度の塩水をつくる。
水500mlに対し大さじ1の塩であらうと黒生かすがでてくる。
汚れができてきたら、ざるにあげて、真水でてばやく洗う。
振り洗い。
クッキングペーパーで水けをふきとる。 - 加熱の仕方
中心部に火が通った目安:最後に箸で押してみて、ぷりっとした感じがあればOK。
または竹串で刺し、仲間で火が通っていたらOK。 - 揚げ物で縮ませない方法
かたくり粉をまぶすことで縮まないようにする。
袋の中でまぶすと、他の調理器具にもウイルスがつかないのでよい。
揚げた後、火だが茶色っぽく変わっていれば火が通っている証拠。
牡蠣を使ったレシピ
- 蚵仔煎(オアチェン)
いかがでしたでしょうか。
牡蠣を美味しく食べるための選び方、調理法について、お分かりいただけましたでしょうか。
冬らしい食材でもある牡蠣。
旬の季節になったら、様々な食べ方を楽しんで、食卓を豊かに楽しくしましょう。