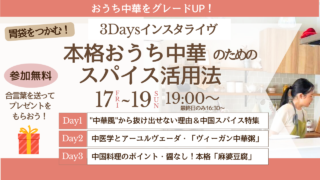真っ赤な宝石のような実がたくさん詰まっている果実、ざくろ。
ビタミンCによる抗酸化作用から、女性に人気の果物です。
ざくろの基礎知識と、普段の食卓に活用しやすいレシピをご紹介します。
ざくろ
有史以前から栽培されている歴史のある果実。
日本には平安時代に中国から渡来し、鎌倉時代には人家で栽培されていたといわれています。
梅雨の時期に花を開き、秋に実を結びます。
日本では山梨で栽培がさかんです。
果実は球形で、直径約7~8cm。
果皮は厚くてかたく、日光に当たると紅色になります。
よく熟したものは特有の香りと甘味があります。
| 分類 | 果実類 | 旬 | 9~10月 |
| 原産地 | 中近東、地中海沿岸 | ||
| 栄養 | 主な成分は糖質で、ビタミンCが豊富。 | ||
栄養
果皮が厚く種子が多いため、廃棄率が高く、可食部は約45%。
主な成分は糖質で、ビタミンCの含有量はやや多めです。
利用・食べ方
生食します。
そのまま食べたり、サラダやマリネ、ヨーグルトに混ぜたりします。
また、果肉が鮮明な赤色(アントシアン系色素)を呈し、甘味もあることから、清涼飲料の原料、ざくろ酒にも利用されます。
トルコでは、ザクロソース(ざくろをしぼって煮詰めた、ざくろ100%の濃縮液)やザクロ酢を料理に使うことが多いです。
ざくろの皮のむき方・ポイント
- ザクロの実の上下の飛び出た部分を切り落とし、包丁で切れ目を入れます。
- 大きめのボウルに水を張り、ざくろの切れ目から裂くように水の中で実を割ります。
どのみち洗うことですし、水の中でおこなうことで汁が飛び散りません。 - 殻から実を外します。浮いた殻を取り除きながら作業をします。実は沈みます。
- 実をすべて取り外したら、目の粗めのざるに上げて、流水で細かい殻や肩を流します。
- キッチンペーパーで水けをふき取り、容器に移して保存します。
アーユルヴェーダの栄養学
アーユルヴェーダの観点からざくろを見ていきます。
アーユルヴェーダの栄養学概要について
>>【アーユルヴェーダの栄養学】食材ごとに決まっている7つの性質
質(Guna)
- 甘いもの⇒冷性
- 酸っぱいもの⇒熱性
動作(Karma)
V↑P↓K↓
味(Rasa)
甘味、酸味、渋味
効果(Prabhava プラッブハーヴァ)
- ビタミンCを多く含む豊富
- 新しい赤血球細胞をつくる。
- 有毒な胆汁をクレンズし、胆管を浄化する。
- 肝臓、血液を浄化する。
- 消化、胃酸、胆石、熱、マラリア性の熱、アメーバ赤痢、多汗、その他のピッタ性の症状に効く。
- おりものやサナダムシにも効果あり。
- マインドを穏やかにし、心肺機能を強化する。
アーユルヴェーダの料理教室(名古屋)
アーユルヴェーダの知識や、アーユルヴェーダ料理を学びたい方は、
愛知県名古屋市の「森の時計」に是非お越しくださいませ。
※オンライン講座も開催しております。
ざくろを使ったレシピ
- ザクロシロップ
- ザクロジュース