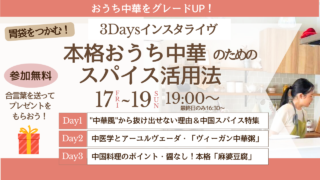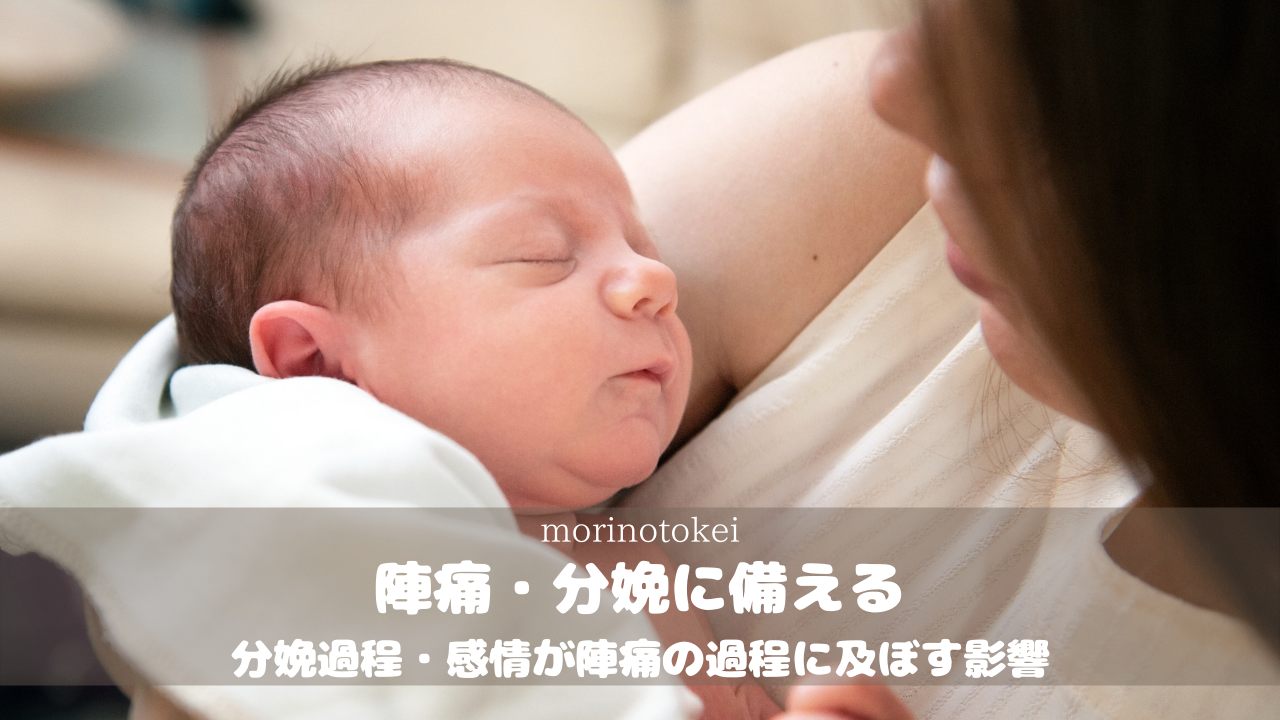妊娠期、身体は胎児を育てるために様々な調整を行ってきました。
いよいよ陣痛・分娩を迎えたら、赤ちゃんと会えるという希望を込めて、深い呼吸を送りましょう。
本稿では、陣痛への備えや、分娩の過程、感情が陣痛の過程に及ぼす影響についてお伝えします。
陣痛への備え
ブラクストンヒックス収縮と呼ばれる前駆陣痛は、赤ちゃんが生まれる準備が出来たという最初のサインです。
この収縮は痛みを伴わず、内側から誰かがお腹をつねってから離したような感覚があるかもしれません。
子宮底が拡大すると、赤ちゃんが楽に骨盤の中に落ちることができ、より頻繁に前駆運動が生じます。
前駆陣痛は、本当の陣痛が始まる数週間前に生じますが、実はこれが、分娩過程の始まりを示します。
どの程度、どのくらいの頻度で前駆陣痛を経験するかは個人差があります。
前駆陣痛を感じたら、間近に迫っている陣痛に備え、身体と感情をメンテナンスしましょう。
深い呼吸やヨガ、パートナーや家族にマッサージをしてもらったり、心が温まるような食べ物を食べたりして、甘やかせてもらいましょう。
ヨガのポーズでおすすめなのは、仰向けの合せきのポーズ (スプタバッダコーナーサナ)のようなリストラティブポーズです。
リラックスできますし、疲れも癒されます。
また、花輪のポーズ (マラーサナ) はスクワットの姿勢なので、分娩過程に備えることができます。
分娩の過程
分娩は大きく3つの段階に分けられます。
- 分娩第1期
- 分娩第2期
- 分娩第3期
分娩第1期
陣痛の開始から、子宮口(子宮頸部)が完全に開く(全開大、約10cm)までの期間です。
分娩第1期は「潜伏期」と「活動期」に分けられます。
潜伏期は陣痛がリズミカルになり、子宮頸部が薄くなり4cmほど開いた状態までの時期を示します。}
初産婦で12時間・経産婦で5時間程度かかります。
活動期は子宮口が4センチから10cm(全開)に開き、胎児の一部が胎盤内に降りてきます。
初産婦で3時間・経産婦で2時間程度かかります。
分娩第一期(潜在期)
分娩第一期(潜在期)は、最初は子宮の収縮の間隔が広く、痛みの強さは人それぞれです。
子宮収縮が強くなり、よりリズミカルになってからも、ゆったりとしたヨガの呼吸法を練習しましょう。
陣痛の間に、骨盤底筋を出来る限り弛緩させて休ませるのです。
プラーナを必要としているお腹に向かって呼吸を送りましょう。
勝利の呼吸(ウジャイープラーナーヤーマ)もこの時期に効果的な呼吸法です。
この潜在期が1番長くかかります。
数時間で終わる人もいれば、24時間たっても終わらない人もいます。
潜在期は、さらに急速で活発な分娩期のために身体を準備している時期です。
この時間に、子宮の平滑筋、子宮頚管が、まもなく起こる急激な拡張に対応する準備をしています。
子宮収縮を乗り越えやすいと感じる体位は人それぞれです。
身体を垂直に保った方が良いと感じる女性もいれば、両脚を広げて座って身体を前傾させたほうが良いと感じる女性もいます。
膝立ちで垂直のままでいるか、スクワットの体勢をとっても良いでしょう。
横になると、重力によって骨盤の後部に圧力をかけることになります。
子宮収縮期の間は、ひたすら休みます。
分娩第一期(活動期)
子宮頚管が3~4センチに拡張すると、陣痛が早まり、子宮頚管が拡張して薄くなっていく速度が早くなります。
この時期の所要時間も個人差があります。
子宮頚管は、赤ちゃんが産道に入ることができるように十分に拡張しなければなりませんが、一旦入ってしまえば、それ以降は赤ちゃんの頭が子宮類管を押し広げるようになります。
陣痛の間隔が短くなると共に痛みも強くなります。
この時期には、ほとんど休んでいる暇はありません。
分娩第2期
子宮口が完全に開大してから胎児を娩出するまでの期間です。
赤ちゃんが産道を通っている間が分娩第2期です。
初産婦では平均45~60分間、経産婦では15~30分間続きます。
子宮頚管が完全に開くと、娩出を始めることができます。
呼吸を止めて身体に負荷をかけないようにしましょう。
完全に息を吐き切って骨盤底を緩めることに集中しましょう。
分娩第3期
胎児を娩出してから胎盤を娩出するまでの期間です。
この段階は数分間で終わるのが普通ですが、最大30分ほど続くこともあります。
いわゆる「後産」の時期です。
感情が陣痛の過程に及ぼす影響
妊娠期中、身体は胎児を成長させるために次のような調整を行ってきました。
- 内分泌系や副腎がホルモンを分泌し、血液や体液の量を増やし、赤ちゃんに送る
- 赤ちゃんの成長に合わせて子宮が拡大することができるように靭帯と筋肉を柔軟にする。
そして、分娩時には子宮が収縮します。
子宮下部が伸長し、子宮頸部は赤ちゃんが出てこられるように大きく開く必要があります。
月経中や妊娠中に活性化する視床下部と下垂体が、子供の誕生においても活性します。
しかし、これらの分泌腺の働きには感情が関係しているため、緊張や恐れ、ストレスを感じたり、神経質になったりすると、内分泌系や自律神経系に直接的な影響を与え、子宮収縮ホルモンやエンドルフィン(痛みに耐える助けをする)の分泌を阻害します。
母体だけでなく、赤ちゃんにも同じことがいえます。
陣痛の際に恐れを感じたり緊張が生じたりしていると、交感神経が暴走し、「闘争・逃走反応」を誘引します。
逆に、落ち着きリラックスしていると、副交感神経が優位になり、子宮頚管を拡張させ、膣壁を引き伸ばすことができるようになるのです。
不適切な呼吸は、身体を硬くさせ、痛みを感じさせ、子宮の収縮が効率的に行われなくさせます。
ゆったりとした意識的な深い呼吸ができれば、分娩の過程を事故なく成し遂げることができるでしょう。