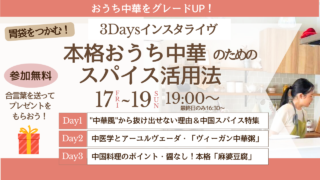4~5月に旬を迎えるたけのこ。
たけのこの基礎知識と、アーユルヴェーダ的な質についてお伝えします。
たけのこ
たけのこといえば春の味覚。
あく抜きなどが面倒臭く、なかなか丸ごと買わないかもしれませんが、春の訪れを感じるために、年に一度は新鮮なたけのこを使った料理を作りたいですよね。
| 分類 | 野菜類 | 旬 | 4~5月 |
| 原産地 | 中国 | 生産地 | 日本、中国、東南アジア |
| 種類 | 孟宗竹、破竹、真竹 | ||
| 栄養 | たんぱく質がやや多く、カリウム、食物繊維も比較的多い | ||
| うま味成分 | チロシン、コリン、アスパラギン酸 | ||
たけのこの栄養
不溶性の食物繊維が多く、カリウムなども比較的多く含まれています。
カリウムは体内のナトリウムを排出する働きをもつので、塩分を多く摂ってしまいがちな人は是非摂取したい栄養素です。
アミノ酸の一種、グルタミン酸やアスパラギン酸を含み、疲労回復に有効です。
保存とあく抜き
えぐ味のもとであるホモゲンチジン酸とシュウ酸は、掘りだしてから時間が経つと、急速に増加します。
そのため、生のまま保存しておくことはできません。
すぐに茹でる、下処理をすることが必要です。
(※下処理の仕方は割愛させていただきます。)
茹でたら皮をむいてさらに10分ほどゆで、水にとって冷まし、水を張った保存容器に入れて冷蔵保存します。
使い方のポイント
部位によって切り方を変えるのがポイントです。
穂先、中央、根元の3つの部位で、繊維のかたさが違うからです。
穂先
柔らかい部分です。
くし切りにし、食感を楽しみます。
中央部分
繊維に沿って切ります。
薄切りにし、ほどよい歯触りを楽しみます。
根元
繊維を切るように食べやすい厚さに切ります。
アーユルヴェーダの栄養学
アーユルヴェーダの観点からたけのこを見ていきます。
アーユルヴェーダの栄養学の概要について
>>【アーユルヴェーダの栄養学】食材ごとに決まっている7つの性質
質(Guna)
- 冷性
※中医学においても寒性に属すとされます。
根菜は体を温める……というような認識があるかもしれませんが、
冷性なんですね。
冷え性や下痢気味の方は食べ過ぎないようにしましょう。
また、少し「重」い性質があるように思います。
動作(Karma)
※私の主観です。
V↑P-K↑
冷やす性質があることから、ヴァータとカパを上げると感じます。
春の野菜なので、カパにはいいものであってほしいのですが。。
甘味と苦味をもつことから、Pを下げるように思いますが、たけのこってえぐ味があり、ちょっとラジャスな感じもするので、Pにもそんなに向いていないように思います。
味(Rasa)
甘味、苦味
消化後の味(Veepaka)
甘味
アーユルヴェーダの料理教室(名古屋)
アーユルヴェーダの知識や、アーユルヴェーダ料理を学びたい方は、
愛知県名古屋市の「森の時計」に是非お越しくださいませ。
たけのこを使ったレシピ
たけのこごはん
春に一度は食べたい、定番の炊き込みごはんです。
材料(作りやすい量:3~4人分くらい)
- 米 2合(360ml)
- 鶏胸肉 100g
- たけのこ(ゆでたもの) 80g
- 油揚げ 1枚
- 小葱 少々
- しょうゆ 大さじ2
- 酒 大さじ1
- 塩 お好みで
作り方
- お米をとぎ、2合分のお水より若干少ない量の水を入れる。
- たけのこは小さめの薄切りにし、鶏肉は皮を除き、小さめの一口大(2~3センチ角)に切る。
- 油揚げは細切りか1cm角に切る。
- ボウルに醤油、酒を入れ、たけのこ、鶏肉を加えてまぜ、10分ほどおく。
- お米の中に4と油揚げを入れ、普通に炊き上げる。
ムラができないよう、全体を混ぜ、10分ほど蒸らす。 - 器に盛り、小葱を散らす。
ポイント
- たけのこごはんむすびにして持っていく時には、少し塩を加えました。
- 薄めの味つけです。
- あしらうものは、小葱のほか、三つ葉などでもいいと思います。
献立例
たけのこご飯のおとも(献立例)。
- たけのこごはん
- お味噌汁(春キャベツとにんじん)
- 天ぷら(かきあげ、たけのこなど)
- ツナと長芋のマヨネーズ和え
- 煮干しのごまみりん焼き
かきあげには、春らしく桜エビを入れたり、さつまいもや人参などを入れて、甘くしてもおいしいですよね。