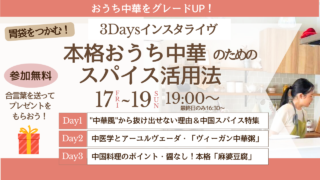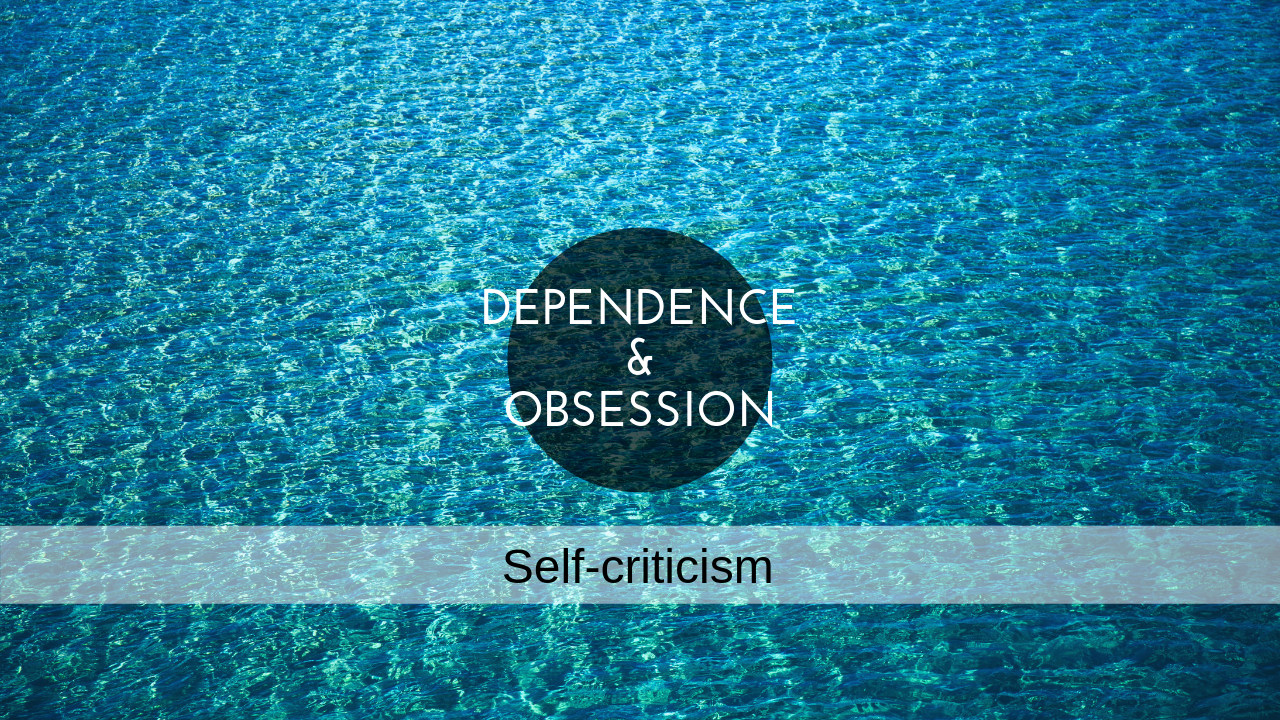煩悩と依存について。
3回目の本記事のテーマは、「クレーシャ(煩悩)に対処する方法」です。
前の記事を読みたい方はこちら
>>誰もが陥っている可能性のある依存とその弊害について
>>アーユルヴェーダとヨガから紐解く依存を生み出す5つのクレーシャ(煩悩)
クレーシャを手放すためには全体のバランスを整える
アーユルヴェーダということで、ホリスティック(総体的)な見方をします。
つらさや苦しさがあると、身体のある部分とか、原因となりそうなあるイベント(出来事)に目をむけがちですが、まず広い視野を持つことで、真の原因と向き合うことができます。
そのため、クレーシャを手放すためには、
ラジャス・タマスが大きくなると、それらの方向に向かっていきがち。
ラジャス、タマスを減らし、サットヴァな性質をより多く取り入れていくことが大切です。
※各アーユルヴェーダの用語が分からない場合は、上の「・」の部分で、名称をクリックすると、詳しい解説の記事に飛びますので、ご参照ください。
全体のバランスが分かったら小さな一歩を踏み出す
けれど、いきなりサットヴァに向かうことはできませんよね。
そこで、タマスからラジャスに向かう提案を1つか2つ、考えてみます。
その中で、自分が一番簡単に取り入れられることを選びます。
取り入れる過程で、いかに自分と向き合うことが大切か気付くようになると思います。
でも、時々、感情的な部分が邪魔をするようになると思います。
心地いい方向に向かいたいと思っていて、実行し始めていても、途中でくじけそうになります。
なので、できれば飽きてやめてしまう前に、成功体験ができるとベターです。
「直接」経験の大切さ
直接的な経験を通して得る知識や「これって本当にいいんだ」っていう感覚がすごく大切なんです。
現代は直接経験の価値が普段の生活で得ることがなかなか難しいですよね。
外からのいろいろな情報に頼ってしまうと、自分に適合できるかどうかの判断ができませんが、本来は直接的経験から自分は何をしたらいいのか学ばなければなりません。
時には自分がやりはじめたことや、いいと思ってやっていたことが間違っていることもあります。
けれど、まずは自分が考えたり気付いたりすることが大切です。
無意識にならないってことです。
アーユルヴェーダの基本的な法則の中で言われていますが、自分が経験することに責任をもつことが大切です。
一貫性をもつ
一貫性というのも有効なはたらきかけです。
何しろ、ある程度継続しないと、結果というのは正しく見えてきません。
小さな取り組みの中に一貫性をもつことも大事ですが、同時に自分の人生の中にも一貫性をもって継続することが重要です。
まとめ
いかがでしたか?
やや複雑な内容でしたので、少しおさらいをしましょう。
- 私たちは何かに依存し、悪い習慣として定着すると、大きな問題につながる。
- クレーシャ(煩悩:無知、自我意識、執着、嫌悪、恐れ)は依存を生み出す。
- クレーシャを遠ざけるためにはマハグナのバランスを整え、サットヴァ(純粋性)の方向に向かうことが重要
- サットヴァの方向に向かうために、最も簡単なことから1つか2つ考え方や行動を変える
- 新たなチャレンジの過程で自分の変化を観察する
- 間違ったやり方であればそれを修正するが、正しいか間違いかが重要ではなく、考えて行動に移したという事実そのものや、観察力が大事。
つまりは過程を人生の経験として楽しむということ。 - チャレンジの過程で成功体験を積めればベスト。
- 成功体験をするには必ず、「直接的」にそれに関わらないといけない
- 成功体験をするには一貫性も大事である