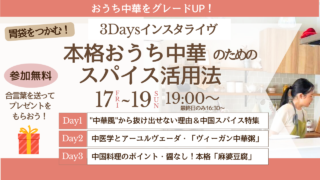アーユルヴェーダの食事におけるポイントをご紹介します。
アーユルヴェーダ式食事法では、食べ物を「どのように食べるか」という姿勢や態度がとても重要です。
アーユルヴェーダの健康の柱「食生活(アハーラ)」
サンスクリット語のアハーラは、「食習慣」という意味で、食事に関するスタイル(ベジタリアンなど)を指すこともあります。
アハーラは、私たちの健康の柱。
現在、私たちのライフスタイルは多様化し、選択肢が広まっています。
個人に合った生活ができそうでありながら、かえって自分に合う選択がうまくできず、バランスを崩してしまいがちだと思います。
私たちが食事について考える時、「何を食べるか」を考えてしまいがちです。しかし、「どのように食べるか」も、とても大切なテーマです。
この記事では、「どのように食べるか」に関するポイントを4つお伝えします。
アーユルヴェーダの詳細についてはこちら
>>【誰でも5分で分かる!基礎知識】アーユルヴェーダとは
また、次からの説明で頻出する「ドーシャ」についても、ご存知でない場合はこちらでご確認くださいませ。
>>【アーユルヴェーダの基礎知識】ドーシャとは
アーユルヴェーダ食事法のポイント
①規則正しい食習慣・食べる時間を決める
人には1日のリズムを刻む「体内時計」が備わっています。
体温や血圧、血糖値などを調節しています。
規則正しい時間に食事を取ることが調節機能維持に役立ちます。
不規則な食習慣、生活は、ヴァータドーシャを悪化させ、焦燥感や混乱、消化不良などを引き起こし、ホルモンバランスも乱します。
食事はなるべく決まった時間に摂りましょう。
アーユルヴェーダが推奨する時間帯別の過ごし方については、こちらの記事でご紹介しています。>>【時間とドーシャの関係】アーユルヴェーダの時間帯別の過ごし方
②食べ過ぎない(腹7.5分目)
「腹8分目」。
昔から日本人に伝わる食事の心得です。
アーユルヴェーダの食事法においても、これは重要です。
なぜ腹7.5分目(食べ過ぎないこと)が良いのでしょうか?
アーユルヴェーダでは、一回の食事でたくさん食べすぎると、消化力(アグニ)が弱まってしまうから、と説明しています。
消化しきれなかった食べ物は、未消化物となります。
アーユルヴェーダではこの未消化物を「アーマ」と呼び、このアーマが病気の素となると考えます。
③ 作り立ての食事
作り立ての、あたたかい食事をいただくようにしましょう。
作り立ての食事からは、新鮮な野菜や果物のプラーナ(生命力、エネルギー)を享受できます。
食べ物にも、トリ・グナがあり、余りもの、作ってから時間が経ちすぎているものは、タマスの要素があります。生命力が失われてしまっている状態です。
サットヴァな食べ物を取ることで、私たちのマインドもサットヴァに保つことができます。
トリ・グナについてはこちらでご確認いただけます。
>>【アーユルヴェーダの基礎知識】マハグナ│サットヴァ・ラジャス・タマス
④ よく噛んで食べる・だらだら食いはしない
消化は口の中に食べ物が含まれた瞬間から始まります。
噛んでいる間に唾液に含まれるアミラーゼなどの酵素が消化を助けてくれます。
よく噛んで食べ、食べ物をより小さくした方が、小腸の微絨毛からの吸収が効率的になります。
また、食事にあまり時間をかけすぎるのもよくありません。
最初のほうに食べた食べ物の消化が始まっているのに、また次の食べ物が入ってくると、消化にばらつきが出てしまいます。
いかがでしたか?
当たり前のことばかりかもしれませんが、実際には、できていないことがあるかもしれません。
ほんの少しの行動の変化が、ご自身にどんな変容をもたらすか、注意深く観察しながら、日々を過ごしていけるといいですね。